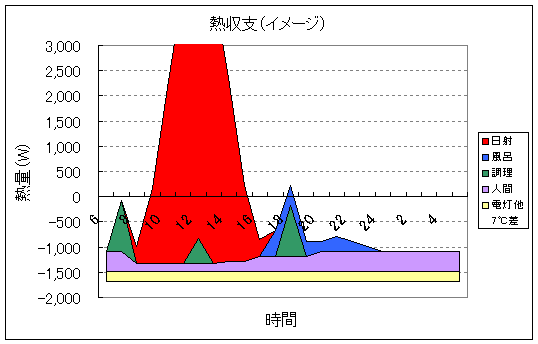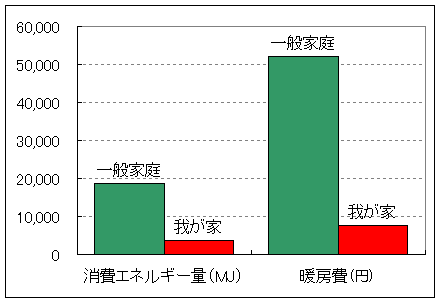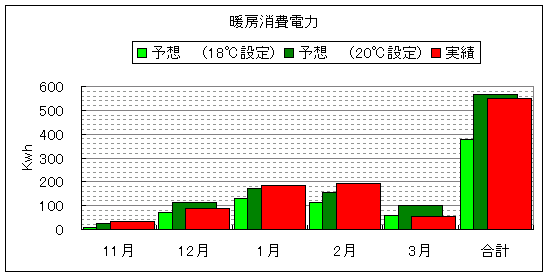| �@ |
|
 |
|
�����T�C�g�ւ̃����N�̓t���[�ł��B�g�b�v�y�[�W�A�ʃy�[�W��킸�A�u���O�Ȃǂ̘b��ɂ��𗧂Ă��������B |
|
�@

|
|
| �@ |
|
|
|
�@��ʉƒ�̌��M��̂����A�g�[���߂銄����26�����x�Ƃ����Ă��܂��B�ȃG�l���l���邤���ŁA�g�[��������ɍ팸���邩�͑傫�ȉۑ�ł��B�䂪�Ƃłǂꂭ�炢�g�[���g���Ă��邩���A�������Ă܂��Ȃ����Ɂu�f�M�����v�Ƃ��ă��|�[�g���܂������A���o�I�ȕi����e1���Ԓ��x�̉^�]�j�����ł��܂���ł����B���x�̓~�́A�G�A�R���̓d�͎g�p�ʂ���������L�^���āA�t�ɂ͂��̓~���������g�[������|�[�g�������Ǝv���܂��B
�@����ɐ�삯�A��~�̃f�[�^�����ɁA�g�[���ׂ�\�����A�g�[����v�Z���Ă݂����Ǝv���܂��B�������A�r���̔M�ʌv�Z�ɂ��ẮA�����܂������̑f�l�ł��邽�߁A�Ԉ�����l����v�Z���s���Ă���\�����傢�ɂ���܂��B�����A���C�Â��̓_������܂�����A���A������������Ə�����܂��B
���M�����ʂ̍Čv�Z��
�܂����߂ɁA�u�f�M�܂Ƃ��v�Ōv�Z�����䂪�Ƃ̔M�����ʂɂ��Ăł����A���܂�ɂ���G�c�������̂ŁA�����������x���グ
�����Ǝv���܂��B�O��̌v�Z�ōl�����Ă��Ȃ������A���A������A���Ȃǂ̔M�������̃}�C�i�X�v���A�_�C���C�g�A�p�{�[�h�Ȃǂ̃v���X�v���A���C�ɂ��}�C�i�X�v������������ƂƂ��ɁA�ʐς��ēx�E�������čČv�Z���܂����B
���ʕʂ̔M����
|
�@ |
���� |
�M�ї����iK�l�j |
�ʐρi�u�j |
�M�����iW/���j |
|
�� |
�� |
0.35 |
57.1 |
20.0 |
|
�M���i������j���ʐς�10�� |
1.05 |
6.3 |
6.6 |
|
�� |
�� |
0.27 |
121.6 |
32.8 |
|
�ǔM���i�ǒ��A�Ԓ��A���j�ǖʐς�18�� |
0.85 |
30.4 |
25.8 |
|
���� |
�i�V��j |
0.21 |
69.3 |
14.6 |
|
�J���� |
���A�h�A |
3.5 |
34.8 |
121.8 |
|
���C |
�i���C�K�v�ʂł͂Ȃ��A���ۂ̊��C�ʁj |
�i��M0..3�j |
�i���C��60㎥�j |
18.0 |
|
|
���v |
239.6 |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
���ʐ� |
128�u |
|
|
�@ |
�@ |
�M�����W���iQ�l�j |
1.87W/�u�� |
���̌��ʁA�����S�̂̔M�����ʂ́A239.6W/���A�M�����W���iQ�l�j��1.87W/�u���ƂȂ�A�O��̌v�Z��葽���������ʂɂȂ�܂����B
���M���x��
�����̔M�����ʂ��킩��A�O�C���ɑ��ĕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��M�ʂ����܂�A���ꂪ�g�[�ʂƂȂ�̂Ōv�Z�͒P���ɍs���܂��B�Ⴆ�A�O�C����10���̎��A�������x��18���ɕۂ��߂ɂ́A���x���~�M�����ʂŁ@�i18��-10���j�~240W/����1,920W�@�ƂȂ�A1.920KW�̔M��₤�K�v������܂��B�G�A�R����COP��4���Ƃ���ƁA���ۂ̏���d�͂�0.48kw�ƂȂ�A�d�C�����P�����|���邱�Ƃɂ���āA�d�C���������܂�܂��B
�@�������A�������ɂ͔M������́i�l�Ԃ�Ɩ��A�d�����i�Ȃǁj������A�܂��A���Ԃ͑��z�̓��˂�����̂ŁA�O������M���擾����ꍇ������܂��B������S�ĕR�����Ȃ��ƁA�{���̒g�[����v�Z���邱�Ƃ��ł��܂���B�܂��A�������̂��M��~����̂ŁA���̒~�M�ʂ��l������K�v������A���n
�ŔM�w�ȂǐG�ꂽ���Ƃ��Ȃ��f�l�̎��ł͑S�Ă��v�Z���邱�Ƃ͂ł��܂���B
�@�����ō�N�̃f�[�^�i�u�f�M�����v���|�[�g���Ɏ��W����12��23���`12/26���j���炠�鉼���𗧂āA��������g�[����v�Z���Ă��������Ǝv���܂��B
���x�ω�
| �@ |
�����C�� |
���r���O�C�� |
�������C�� |
| �Œ� |
�ō� |
��7�� |
��8�� |
��7�� |
��8�� |
| 12/23 |
5.6 |
13.0 |
14 |
15 |
15 |
16 |
| 12/24 |
6.5 |
12.0 |
14 |
15 |
15 |
16 |
| 12/25 |
6.3 |
11.2 |
14 |
15 |
15 |
16 |
| 12/26 |
5.7 |
10.9 |
14 |
15 |
15 |
16 |
12��23���`12��26���́A��������V��͐���ŁA�O�C���̕ω����قړ������������Ă��܂��B���̎��A�܂��G�A�R�������t�����Ă��Ȃ������̂ŁA���g�[��Ԃł̐����ł����B�����Œ��ڂ������̂́A���r���O�C���Ə������C���Ƃ��ɖ����莞�ɂ͓���
���x���������Ƃł��B��7���̃��r���O�́A�O������̔M�̗������Ȃ��A�܂��A�����̔��M���Œ�ŁA�ł������������鎞�Ԃł��B���̎��Ԃ̎������������Ƃ������Ƃ́A�Œ�C��+X��=���������藧���Ă���Ƃ������ƂŁAX�͊T��7�`8���ƂȂ�܂��B
�@��������ς���ƁA�M���x�͒�7���̎��_�ŁA�Œ�C��+7�`8���ɂȂ�悤�ȃo�����X�ł���Ƃ������ƂŁA�������ɍl����A�s�����Ă���M�ʂ��v�Z���邱�Ƃ��ł���͂��ł��B�r���̔M���x�͂킩��Ȃ��̂ł����A�Œ�C��+7���Ƃ��āA������M���x��z�������̂��A�ȉ��̕\�ƃO���t�ł��B
���ԕʔM���x�i�C���[�W�j
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�P�ʁFW |
�@ |
|
�@ |
���� |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
�@ |
|
���M |
1���� |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
�@ |
|
7���� |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
�@ |
|
���M |
�d���� |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
�@ |
|
�l�� |
400 |
400 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
�@ |
|
���� |
�@ |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
�@ |
|
���C |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
�@ |
|
���� |
0 |
0 |
340 |
1,500 |
3,500 |
5,500 |
7,500 |
5,500 |
�@ |
|
�M���x |
-1,314 |
-313 |
-1,222 |
-61 |
1,940 |
3,941 |
6,442 |
3,943 |
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
���� |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
�@ |
|
���M |
1���� |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
�@ |
|
7���� |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
�@ |
|
���M |
�d���� |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
�@ |
|
�l�� |
200 |
200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
400 |
400 |
�@ |
|
���� |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
�@ |
|
���C |
0 |
0 |
0 |
500 |
400 |
300 |
200 |
300 |
�@ |
|
���� |
3,500 |
1,500 |
340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
�@ |
|
�M���x |
1,994 |
-5 |
-1,064 |
-903 |
-2 |
-1,101 |
-1,100 |
-999 |
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
���� |
22 |
23 |
24 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
���v |
|
���M |
1���� |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-5,760 |
|
7���� |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-1,680 |
-40,320 |
|
���M |
�d���� |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
4,800 |
|
�l�� |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
7,300 |
|
���� |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,500 |
|
���C |
200 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
|
���� |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29,180 |
|
�M���x |
-1,098 |
-1,197 |
-1,296 |
-1,319 |
-1,318 |
-1,317 |
-1,316 |
-1,315 |
0 |
���v�Z�����i���藝�R�j
���M�ʁF�����̔M�����ʂ��
���M�E�d�����F�ҋ@�d�͂��T��200W
���M�E�l�ԁF��l100W�A�q��50W�Ƃ��Čv�Z
���M�E�����F�Ȃ�ƂȂ�
���M�E���C�F5,000W�i�����̔M�ʁj�~0.6�i�K���j��U�蕪��
���M�E���ˁF�M���x���[���ɍ��킹�邽�߂ɋt�Z
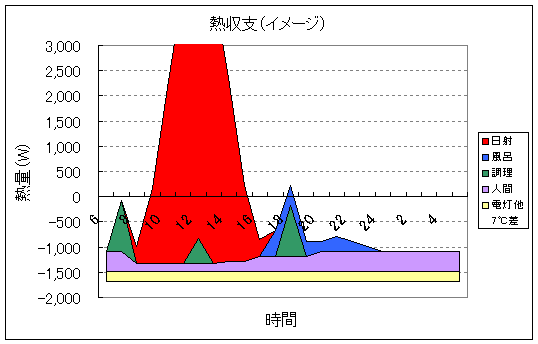
��̕\�ƃO���t�́A�s�m���ȗv�f�ɂ��z���ł����Ȃ��̂ł����A���˂��Ƃ̒g���������E����傫�ȗv���ł��邱�Ƃ𗠕t���錋�ʂƂȂ��Ă��܂��B�����A���z�����炸�A���˂��܂������Ȃ�����
�������Ɖ��肷��ƁA�����M�����̔M���x�ł͔M�����W���iQ�l�j1.87W/�u���̉Ƃ������Ă��Ă��A�O�C���Ǝ����̍��͂킸��3�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�t�ɐ����M������3�����グ����Ƃ����������ł��܂��B�q�����������Ĉ�l�O�ɔM���o���悤�ɂȂ�A�Ƃ̒��͂���1�������Ȃ�܂��B
���s���M�ʂ̌v�Z��
�O�q�̉����i�����͊O�C��+7���ŔM���x�̃o�����X���Ƃ�Ă���j�����������ƂƁA�Ǝ��̂̒~�M�ʂ����邱�Ƃ�O��ɁA������18���ɕۂ��߂̕s���M�ʂ𓌋��̕��ϋC�����狁�߂Ă݂܂��B
�O�C����18��-7���i�M���x�v���X���j��11������������ꍇ�A���̍����s�����x�ɂȂ�A�s���M�ʂ́A���̉��x��240W/���i�M�����ʁj�������ĎZ�o���܂��B
���ԕʕs���M��
|
�@ |
���� |
03�� |
06�� |
09�� |
12�� |
15�� |
18�� |
21�� |
24�� |
���v |
|
11��1�� |
�O�C���i���j |
13.5 |
12.8 |
15.0 |
17.8 |
18.3 |
16.9 |
15.6 |
14.4 |
�@ |
|
�s�����x�i���j |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�s���M�ʁiW�j |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�` |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
12��31�� |
�O�C���i���j |
4.5 |
3.9 |
5.4 |
9.0 |
9.9 |
8.2 |
6.8 |
5.6 |
�@���v |
|
�s�����x�i���j |
6.5 |
7.1 |
5.6 |
2.0 |
1.1 |
2.8 |
4.2 |
5.4 |
�@ |
|
�s���M�ʁiW�j |
4,700 |
5,133 |
4,049 |
1,446 |
795 |
2,024 |
3,037 |
3,904 |
25,088 |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�` |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
3��30�� |
�O�C���i���j |
8.8 |
8.2 |
10.6 |
13.1 |
13.8 |
12.5 |
11.1 |
10.1 |
�@���v |
|
�s�����x�i���j |
2.2 |
2.8 |
0.4 |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
0.9 |
�@ |
|
�s���M�ʁiW�j |
1,591 |
2,024 |
289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
651 |
4,555 |
���C�ے��̉ߋ��f�[�^�ł͋C����3���Ԃ����Ȃ̂ŁA�s���M�ʂ�3���ԕ��Ōv�Z�B
11��1���`3��30���̕s���M�ʂ����ʂɏW�v���ACOP=4�̃G�A�R�����g�p�����Ɖ��肵�ĕK�v�d�͗ʂ��v�Z���܂��B
�K�v�d�͗ʁi24���ԁj
|
24���ԑS�َ���18�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
11�� |
12�� |
1�� |
2�� |
3�� |
���v |
|
�s���M�ʁikwh�j |
51 |
497 |
931 |
821 |
410 |
2,710 |
|
�K�v�d�͗ʁikwh�j |
13 |
124 |
233 |
205 |
102 |
677 |
��L�̌��ʂ�24���ԑS��18����ۂ��߂ɕK�v�ȓd�͗ʂł��B�������A�Q�Ă���ԂƁA���Ԃ̏\���ȓ��˂̂��鎞�ԑт͖����ɒg�[���^�]����K�v�͂���܂���B���ۍ�~�̏����Ɩ�̉^�]�����ł����B�Ȃ̂ŁA6�`12�A18�`24���̉^�]�ɍi���čČv�Z���Ă݂܂��B
�K�v�d�͗ʁi���Ԍ���j
|
12���ԑS�َ���18�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
11�� |
12�� |
1�� |
2�� |
3�� |
���v |
|
�s���M�ʁikwh�j |
28 |
284 |
512 |
448 |
231 |
1,503 |
|
�K�v�d�͗ʁikwh�j |
7 |
71 |
128 |
112 |
58 |
376 |
���\���g�[�
���ʒg�[��
|
12���ԑS�َ���18�� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
11�� |
12�� |
1�� |
2�� |
3�� |
���v |
|
�d�͗ʁikwh�j |
7 |
71 |
128 |
112 |
58 |
376 |
|
�d�C�����i�~�j |
140 |
1,419 |
2,561 |
2,241 |
1,156 |
7,517 |
�Ƃ������ʂ��ł܂����B�d�C�����P����20�~�Ōv�Z���Ă��܂����A���G�Ȏ��ԑѕʒP���Ɍׂ��Ă���̂ŁA���ۂ̗����Ɣ�r���邱�Ƃ��ł��܂���B�������A�g�p�d�͗ʂ͎������܂��̂ŁA�t�ɂ͂��̗\�z�ʂ�ɂȂ������ǂ����̔�r���\�ł��B��~�̑S�̂̓d�C�������犨�Ă��Ă��A�����������Ă�Ǝv���܂��B
����ʉƒ�Ƃ̔�r��
�Ō�ɁA�䂪�Ƃ̒g�[���ʉƒ�Ƃǂꂭ�炢�Ⴄ�ł��낤�����r���Ă݂����Ǝv���܂��B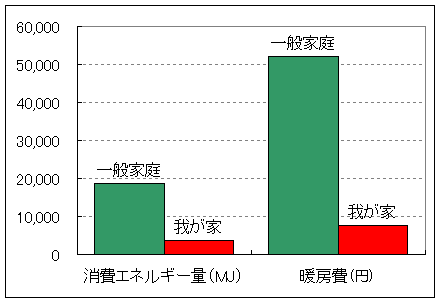
�@�܂��A����G�l���M�[�ʂŔ�r���Ă݂܂��BNEDO�̎����ɂ��ƁA�����ʐ�125�u�̌ˌ��Z��̕W���G�l���M�[����ʂ͎�����ȃG�l��W�n���83,109MJ�ƂȂ��Ă��܂��B���̓��A�g�[��18,711MJ�ŁA�䂪�Ƃ̗\��376kwh��ϊ��i1kwh=9.76MJ�j�����3,669MJ�ƂȂ�܂��B�Ȃ�ƁA��ʉƒ�̂P�^�T���x�̃G�l���M�[����ōςނ��ƂɂȂ�܂��B
�@���ɋ��z�Ŕ�r���Ă݂܂��B��ʉƒ�̌��M���26�����g�[��Ƃ������Ƃ́A���M��N��200,000�~�������Ƃ���ƁA�g�[��͖�52,000�~�ɂȂ�܂��B����ɑ��ĉ䂪�Ƃ́A�d�C�����P��20�~�Ōv�Z���A�킸��7,517�~�B��P�^
�V���x�̒g�[��ōςނ��ƂɂȂ�܂��B
�@���̒f�M���\�邽�߂ɁA100���~�Ɖߍ��ȍ�Ƃ𓊂����킯�ł����A�����{���ɒg�[��v�Z�̒ʂ肾�����Ƃ���ƁA��Ƃ͕ʂƂ���100���~�͕������g�[��23�N���Ō�������v�Z�ɂȂ�܂��B�I�[���d���⑾�z�����d�Ƃ͈���āA�f�M�͉��܂���̂ŁA�m���ɉ���ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�{���ɂ���Ȑ����ɂȂ��
���ȁH���ʂ͏t�܂ł��҂����������B
�����g�[��
�����܂ŗ���ƁA����ɂƍl���Ă��܂��~�[�����B�������̂��Ɩ��g�[�ɂł��Ȃ��ł��傤���H�䂪�Ƃ̃E�B�[�N�|�C���g�͉��Ƃ����Ă����ł��B���ˎ�荞�݂̂��߂ɑ傫���������́A�t�ɔM������傫�����Ă��܂��A������̔M�����ʂ͑S�̖̂�50���ɋy�т܂��B��ʏZ����ƌ���������Ȃ̂ł����A���������P�ł���Ζ��g�[�����ł́E�E�E�B
�@�����ōl�����̂��A�呋�ɓ��������t���A�M���������炻���Ƃ������ł��B�������A���������t����ɂ͑����̔�p�������邽�߁A���݂̓y���f�B���O���ł��B�f�M���C��p�̂P�^�R��⏕���Ă����NEDO�̂��肪�����������Ƃ�3�����ɂ���̂ŁA���̎��ɍēx�������邱�Ƃɂ��܂����B
�@���Ȃ݂ɁA�呋9���ɓ��������t�����ꍇ�A�M�����ʂ�197W/���iQ�l��1.54�j�܂ʼn����邱�Ƃ��ł��A�\������G�l���M�[�ʂ�1,745MJ�A�d�C������3,576�~�ƁA����\���̂���ɔ����ɗ}���邱�Ƃ��ł��܂��B���������̑Ή���70���~�Ƃ����̂͂��܂�ɂ��������܂��B�u���g�[�Z��Ƀ`�������W�I�v�Ƃ��̊���
�A�ǂ����̊�Ƃ��X�|���T�[�ɂȂ��Ă���������Ȃ�A1,745MJ�͉䖝���Ċ��S���g�[���������H���܂��B
|
�@�ȃG�l���K��Ԃ͑��K���X����I
�@��y�ɓ\��āA���ꂢ�ɂ͂����鐅�\��
�@�^�C�v�̍��f�M�f�ނƋ�C�w�̃_�u�����ʂ�
�@��g�[�������啝�ɃA�b�v���܂��B |
2007�N11��
���������ʁi�lj��j��
�������x��18���ŃV�~�����[�V�����������̂́A�G�A�R���̐ݒ艷�x��18���ł͏��X�������܂����B�u�䖝�����ɏȃG�l�v�����b�g�[�Ȃ̂ŁA�G�A�R���̐ݒ��20���ɂ��Ă���܂��B���̂��߁A20���̏ꍇ�̃V�~�����[�V�������lj����܂����B
�\���Ǝ���(2007�N�`2008�N)�̔�r
|
�@ |
11�� |
12�� |
1�� |
2�� |
3�� |
���v |
|
�\���@�@�i18���ݒ�j |
�d�͗ʁiKwh�j |
7 |
71 |
128 |
112 |
58 |
376 |
|
�����i�~�j |
140 |
1,419 |
2,561 |
2,241 |
1,156 |
7,517 |
|
�\���@�@�i20���ݒ�j |
�d�͗ʁiKwh�j |
24 |
115 |
173 |
154 |
100 |
566 |
|
�����i�~�j |
480 |
2,300 |
3,460 |
3,080 |
2,000 |
11,320 |
|
���� |
�d�͗ʁiKwh�j |
32 |
89 |
184 |
191 |
54 |
550 |
|
�����i�~�j |
640 |
1,780 |
3,680 |
3,820 |
1,080 |
11,000 |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
������20�~/1kwh |
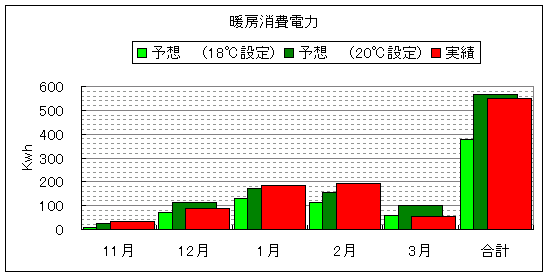
�������̓d�C�����A�����������������M����Ō��\���Ă��܂��B
�y�g�[��\���z
2008�N3��
�@
|
�@
|
�@ |
|
�@ |
|
|
���T���̏�Ȃ�������A
������Ō������Ă݂܂��傤�I |
|
 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
|